朝イチの回を観ながら思った。
新宿武蔵野館は、エンニオ・モリコーネを口実にして、政権交代が叫ばれる昨今の日本の政治事情や、いよいよ近づいてきたアメリカ大統領選に向けて、「左派系の社会派映画」を上映したかっただけなんじゃないだろうか?(笑)
本作はいわゆる「法廷映画」である。
それも、『十二人の怒れる男』や『推定無罪』、『レインメーカー』などと同様、捜査シーンより法廷内シーンのほうが圧倒的に多い、ゴリゴリの法廷闘争ものであり、しかも歴史上「冤罪で無実のアナーキスト二人が強盗殺人罪で死刑に処せられた」ことがわかっている「不当な」裁判の記録でもある。
その意味では『裁かるるジャンヌ』のような「宗教裁判」「魔女裁判」ものの気配も漂わせている。すなわち、これは国家によって悪と認定された人々が、法治主義を偽装した「権力による断罪」によって、人権を無視して電気椅子へと送り込まれた恐ろしい歴史的事実を告発する映画なのだ。
内容としては当然すこぶるつきに政治的な映画だし、当時の州知事や判事、検事に対して大変批判的である。一方でリベラル(アナーキストと訳される)に対しては総じて宥和的で好意的だ。これは、左派勢力が伝統的に強いイタリアで、特に映画業界には極左的なスタンスの人間が多いという状況がモロに反映している部分もあるだろう。
僕個人は決してアナーキストや極左勢力に殊更のシンパシーがあるわけではないし、自らの生きづらさを社会や国家や時の政権のせいにして、あたら正義を振りかざしているような手合いとは距離を置いて生きている。
ただしこのスタンスは、なんだかんだいってそれなりに生きやすい日本で生活しているからそう言えるのであって、最低限の社会正義や人種意識や法的公正さすら認められない社会であったならば、その限りではない。
本作で描かれるアメリカの1920年代というのは、まさに「変革されるべき」不平等と不誠実がはびこる極端なWASP至上主義の時代だった。
本作における検事&判事&陪審員は、明快すぎるほどの「悪」として描かれる。
だから、本作を観ているあいだは、僕も十二分に権力者に対してムカつくことが出来た。
検事の差別感情剥き出しの態度にいきどおり、判事のあり得ないような不公平な姿勢に、おおいに義憤に駆られる。
というか、昔から欧米の法廷ものを観ていると、出て来る弁護士や検事の手腕次第であまりに裁判結果に差異が生じるようなシステムになっていて、ここまでプレイヤーで左右される裁判ってどうなのかしらんと思わせられることが多いんだけど、今回のは本当にやり口がひどすぎる。ここまで恣意的で、被告に対して敵意も侮蔑も隠さないような議事進行が許されるなんて、本当に許しがたい。
一方で、法廷劇としてはなんとなく「ぬるい」印象を与える点は否めない。
事実に即して物語が組み立てられている以上、実際そうであったのなら変えようがない部分もあるのかもしれないが、いろいろもう少しやりようがあっただろう、という気もする。
まず、サッコにもヴァンゼッティにも、かなり明快な「アリバイ」があるのに、そこが判事によって証拠として採用されないというのは、さすがに無理押しが過ぎる。これが本当なら、そりゃあ暴動も抗議も起きるよなあって話。特に移民局の官吏の証言と入館メモを「シンパの偽証」として切って捨てるのは、まあまああり得ない(これを信頼できないと言い出したら、何一つ証言など採用できなくなる)。てか、自分が弁護士ならもっと「アリバイ」の証明に命をかけるし、最終弁論などでもそこを強調するけどなあ。
明確に偽証している人間が複数名判明しても、別に真犯人に当たる人物が名乗りをあげても、それらがすべて「弁護士による強要」として証拠不受理になっちゃうというのもあまりに理不尽に過ぎるし、逆に言うと弁護側はもっと慎重かつ組織的に立証すればいいのにとつい思ってしまう。
まあ何にせよ、あの判事は何も認める気がないんだから、どうしようもないのだろうけど。判事の罷免要求や交代要求の手続きってのは、当時存在しなかったのかなあ。
だからといって、ヴァンゼッティのようにあの場所で熱く政治的な演説をぶっても、法廷闘争上はマイナスの効果しか生まないのも分かり切っているし、いろいろもやっとする。
全世界であそこまでの反対運動が巻き起こっていて、対応を協議しているトップクラスがマサチューセッツ州知事というのも、若干気になるところ。
あれだけ世界中で問題視されれば、国家(=大統領)が再審の判断に暗に介入してきそうなものだけど。
だって、あそこまであからさまな恣意的な議事進行が記録に残っていて、あれだけの反対運動が世界中で巻き起こっているのに、法秩序の権威のためにごり押しで有罪を確定させて死刑執行に突き進んでも、何一つボストンの法曹界にもアメリカ国家にも、プラスとなる要素なんてないと思うんだよね。
逆に、あれだけの反対運動が起きているのに、それをうまく超法規的措置へとつなげていけない支援グループの「政治力」の無さにもいらっとさせられる。
事件が政治問題化してしまった以上は、逆にアメリカとしても一歩も引けない状況になってしまったということか。
というわけで、無理くり二人を死刑に追い込もうとする連中にムカつきながらも、ここまで相手側のやり口がズサンでつけ入る隙のある状況なのに、二人を救う手段を見出せない弁護側に対するもどかしさも、ずっともやもやと感じながら観ていたのだった。
― ― ―
ちなみに、アバンで展開される、イタリア人居住区を官憲が襲撃するモノクロのシーケンスは、言葉を喪うほどに素晴らしい。
画面内のモチーフが徹底的に統制され、様式化されている。
斜めに移動する警官隊の群れ。
路上に延びる影と建築物が交錯する。
入念にリハーサルされたマスゲームのような美しい動き。
引きとアップを切り替えるカメラのリズムが、静寂から暴力への転調と呼応する。
スクリーンの端々まで、監督の意図したとおりに人が動き、監督が思い描いたとおりのヴィジョンが現実化している。
このひりついた緊迫感と透徹した演出を全編にわたって行き渡らせることに成功していたら、本作は他のネオ・リアリズモの名作群に負けない傑作に仕上がっていたはずだ。
だが、映画は本編のカラーパートに入ってからは、比較的まっとうで癖のない演出とカメラワークに落ち着いてしまう。
もったいないといえばもったいないが(せっかくやろうと思えば出来ることがわかっているスタッフなのに……)、やりたかったことはそういうエッジのきいたドキュメンタリー・タッチの映画ではなかったのだろう。
「もっとハードでリアルなタッチのドキュメンタリー風映画」を志向すればきっと傑作になり得たのに、「若干情緒的で観客を煽るような政治的に偏向した映画」に仕上げたせいで損をしているという印象は、実はエンニオ・モリコーネの音楽とも無関係ではない。
モリコーネ・ミュージックとして、『死刑台のメロディ』は傑作サントラの一つとして知られている。とくにジョーン・バエズが歌う「サッコとヴァンゼッティのバラード」と「勝利への賛歌」は、ほぼすべてのベスト盤に収録されている、誰もが代表曲として知る名曲だ。
だが逆に、映画にとってモリコーネの音楽は本当にふさわしかったのだろうか?
そう言われると、僕個人の意見は「NO」としか言いようがない。
先に言っておくと、先般上映されたジュゼッペ・トルナトーレの『モリコーネ』の感想でも書いた通り、僕はエンニオ・モリコーネの大ファンであり、マニアとは言えないまでもかなりのサントラを所有しているし、その素晴らしさは人一倍知っているつもりだ。
だがやはり、それでも僕は思う。モリコーネ・ミュージックは、こういう告発型の社会派映画には向いていないと。
だって、せっかくのシュアでシリアスな「ドキュメンタリー」が、あのメロウで情動的な音楽が流れることで、『世界残酷物語』のようなモンド映画の「モキュメンタリー」みたいに感じられてしまうから。どうしてもモリコーネ節がオルトラーニ節みたいに聴こえてしまうから(笑)。
モリコーネの音楽は心を動かす力が強すぎて、どうしても観客を「煽動」してしまう。
主人公をヒロイックに見せてしまうし、共感を呼んでしまうし、正義を鼓舞して悪を断罪するような情緒的な反応を引き起こしてしまう。
でも、たぶんこの手の映画にとって、そういうのは「余計」な要素なのだと思う。
似たような社会派的な題材でも、ベルナルド・ベルトルッチは『1900年』でモリコーネ・ミュージックを理想的な形で用いていた。あのくらい叙事詩的で、ヒロイックで、壮大なスケールの歴史絵巻に仕上げるなら、モリコーネはぴったりの巨匠なのだ。
だが、本作のような密室法廷劇では、モリコーネのクセのある音楽は、たぶんとても使いづらい素材だったはずだ。
結局のところ、監督のジュリアーノ・モンタルドはモリコーネ・ミュージックをかなり「もてあましている」気配が強い。実際、本作のなかで音楽が流れるシチュエーションは、きわめて限定的だといってよい。要するに、モリコーネがこの映画のために作った曲は「あまり中で使われていない」。
パンフによれば、モリコーネは主題曲の「サッコとヴァンゼッティのバラード」だけで曲調の違う3パターンの楽曲を作っているらしいが、映画のなかで使用されたのはその1パターンだけだ。映画の大半を占める法廷内のシーンでは、そもそもほとんど音楽自体が流れない。たまに出て来る回想シーンとか街頭デモのシーンとかでいきなり音楽がかかるから、曲が「どこか悪目立ち」する。
結果的に、ジョーン・バエズの扱いにしても、ベトナム反戦歌みたいなきわめて情緒的でメッセージ性の強いものになっていて、個人的には若干むずがゆい感じだった。
いやあ、当然ながら曲自体はホントに良い曲なんだけどねえ(笑)。
当時の邦題を担当した宣伝マンも、モリコーネの音楽に強い衝撃をうけたからこそ、わざわざ『死刑台のメロディ』ってタイトルをつけたんだろうし(原題はただの『サッコとヴァンゼッティ)』。
ただ、どうも僕にとっては、使い方も、映画との兼ね合いも、あんまりしっくりこなかったという印象でした。なんかすいません。
とはいえ、こうやってサントラのみで知っていた映画を映画館で観させてもらえたのはありがたい限り。
以下、備忘録。
●あれだけ『荒野の用心棒』と『夕陽のガンマン』が好きだとか言って回っているのに、エンド・クレジットを見るまでヴァンゼッティがジャン・マリア・ヴォロンテだって気づいていなかった。ただただ自分が恥ずかしいです(笑)。藤本隆宏みたいな俳優さんだなとか思いながら見てました。
●こういう裁判で、容疑者二人がずっとツーマンセルで行動させられているのも(刑務所すら同じで、しかもお互いが見える範囲で収監されている)、今の感覚からすると不思議な感じがする。共犯の被告って、そういうもんだっけ?
あと法廷に出廷するときって、被告はずっと蝶ネクタイ着用のまあまあ良い格好してるのな。
●電気椅子のことも、一応死刑台って言って良いんだろうか?
●パンフでセルジオ石熊さんの解説を読んでいたら、ジュリアーノ・モンタルド監督の作品として、『クローズド・サーキット』(78)というテレビ映画が紹介されていて、いわく「ジュリアーノ・ジェンマ主演のマカロニ・ウエスタンを上映中の映画館で連続殺人が起きるというルイス・ブニュエル的不条理心理劇」らしい。やっべえ、超観てえ!!
●もし数年前にこの映画を観たのなら、「1920年代のアメリカの裁判なんて、たかだかこんな程度のもんだったんだなあ」といった印象を持っただけだったろうが、2024年になって改めてこれを観たとき、裁判手続きのインチキぶりや恣意的な判決、ごり押しの法執行といった部分が、たとえばロシアで現在行われている裁判あたりと「なんにも変わっていない」ことに衝撃を受ける。人間というのは、本当に愚かしい生き物だと思う。

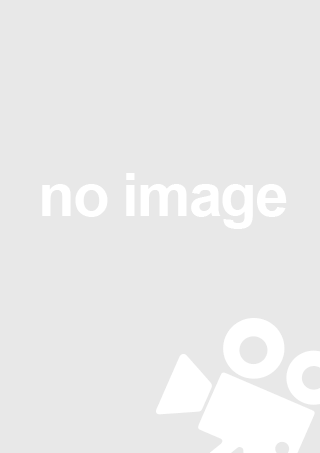


 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 この世界の片隅に
この世界の片隅に 007/ノー・タイム・トゥ・ダイ
007/ノー・タイム・トゥ・ダイ マスカレード・ホテル
マスカレード・ホテル ダンケルク
ダンケルク ミッション:インポッシブル デッドレコニング
ミッション:インポッシブル デッドレコニング 1917 命をかけた伝令
1917 命をかけた伝令

















![ジャン=リュック・ゴダール Blu-ray BOX Vol.2/...[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51cWYjBK0KL._SL160_.jpg)






